今回は、日常生活でできる「思考する脳の領域を刺激する訓練」を
紹介します。記憶する領域から思考する領域への情報受け渡しや
スムーズな切り替えに役立つと思います。
中学受験生はもとより、小学生低学年のお子さんにも有効と思います。
お子さんが小学生以下の場合、家族で外出することは多いでしょう。
旅行、レジャー、外食、親戚や知人に会いに・・・。
この楽しみごとが含まれる外出時を利用しない手はないのです。
子供たちにとって、外出して楽しいことをすることは、脳が活発に動く
こと。興味があって、楽しい。すでに脳の受け入れ準備はできています。
このような、楽しい外出時に課題(調べて発表)を与えてみましょう。
テーマは親御さんが決め、そのことについて事前に子供の力で調べさせます。
現地に着いたら、必ず発表の時間と質問の時間、確認の時間を準備してください。
テーマを親御さんが決めると言いましたが、ジャンルを地理や歴史に偏らないように
するためです。
たとえば、海水浴に行くという計画をします。ただ海水浴するだけでは単なるレジャー。
そこで、海水浴に行く場所の名産、産業、有名人、歴史などの中から、ジャンルとテーマ
を決め、お子さんに調べさせる。当日は海水浴の後に発表させます。
もし、現地に確認できるお店、資料館や見学できる工場があれば最高です。
海水浴という外出なので、テーマを地元名産の「干物」にしたとします。
かならず、発表する内容に「なぜ」が含まれるようにさせてください。
魚を干物にする理由や価値が「なぜ」になります。
・ 保存させる
・ 軽くなるから運びやすい
・ 獲れる季節が限られているから
・ 味がよくなる
いろんな「なぜ」を発表してくれます。
しかし、発表はしたものの、「なぜ」が実感できないのが大半なので、
現地で実物を見て、さわり、更にお子さんにお店の人や資料館で
地元の人に質問させてみる。
調べ⇒発表し⇒見て触れて⇒聞く。自分の調べた世界と実際の世界が接触し、
リアルに「経験」の中に吸い込まれる。これが思考の領域を使う訓練になります。
お気づきですか?この一連の流れの中に「覚える」という領域はほとんど
ありません。リアルに「経験」の中に吸い込ませる。思考の領域が処理している
ため、忘れるという自動消去もかかりません。
ただし、6年生になったら外出は1ヶ月に1回です。
自宅学習する時間が大切だから。
幼児には、親御さんから「なんでだろうね」と聞く習慣をつけましょう。
動物園に行って親御さんが「象さんはハナが長いね」と言うのと、
「象さんはなんでハナが長いのかな」と言うのでは、お子さんにとって
脳の使い方が違うのです。
お子さんが親以外の人に「どうして象のハナが長いの」と聞くようになれば
しめたもの。思考で理解する始まりだから。
将来の天才児への第一歩かも知れません。
算数は「覚えない」で「体験理解」する思考科目として
習慣がついたとき、回路がつながるがごとく成績が向上する。
すごく不思議な科目です。いや、それ以上に生徒の可能性に驚きます。
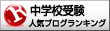
←応援お願いします。
 [0回]
[0回]
PR


