タイトルをご覧になって、?と思われた方がたくさんいらっしゃることでしょう。
今日は、イッセイ会の指導基軸なるもの少し紹介いたします。
長年、受験生に接していますと、生徒達の頭の中は、まさに小宇宙に感じてなりません。
で、何を言いたいかというと、
この小宇宙、規則というか法則というか、パターンのようなものがあり、その規則や
パターンを踏まえて学習させると、生徒はステップアップする。
要は、このパターンに対し効果的に、時には逆手にとって指導するのが
イッセイ会の指導基軸なのです。
私は、大脳生理学者でもなければテレビに出演されているような脳科学者でも
ありません。しかし、自宅学習(しかも低コスト)で中学受験に成功させるには、
大手広域塾のミニ版では生徒達を満足に導くことはできません。
指導基軸は脳仕組み、とりわけ生徒がどのように脳を使って学習するかを
考察して出来上がりました。
勉強する、学習するということは、2つの機能(脳の領域)を使っています。
・ 思考する脳
・ 記憶する脳
思考する脳は、仕組みを理解し、応用して同じ系統の問題を克服します。
しっかりインプットすれば、なかなか消去され難い特徴があります。
算数全般、国語の読解と記述、理科の物理分野と地学分野(特に月、星、太陽)
で良い成績をとり、良い成績を維持するには欠かせない脳の領域です。
記憶する脳は、暗記することであって、「覚える」こと全般を支配しています。
残念ながら、多かれ少なかれ、誰でも時間経過とともに自動消去されます。
漢字や熟語、作者と作品名、理科の生物分野と化学分野、歴史と地理
で良い成績をとり、良い成績を維持するには欠かせない脳の領域です
また、訓練しないと個人ごとに記憶できる量や期間に差が生じるのも
記憶する脳の特徴です。
生徒たちですが、誰でも上記2つの脳の領域を持っています。
ただし、共通して言えることは、全ての教科の学習に対し、新しい項目は、最初は全て
記憶する脳から使います。これはおそらく、人類の脳の仕組みからくるのでしょう。
算数の水槽に張った水に錘を入れて水位が上昇するメカニズム理解も地理の山脈名も
学習するにあたり最初は「記憶する脳」の領域が処理をします。
この時点で、「なぜ、なぜなんだ」という観念が発生すると、記憶する脳の領域では、
手に負えなくなり、思考する脳の領域に仕事をバトンタッチして、その仕組みを
解釈していきます。思考する領域は構造理解をつかさどるのが役務なのでしょう。
バトンタッチされた複雑なデータを見事に解釈していきます。
一方「なぜ、なぜなんだ」が必要なく「はい、そういうことね」という概念で終了する
暗記的データは、そのまま記憶する領域が受け持つようです。
学習よろず請負所的な「記憶する領域」ですので、受け取るデータは全て
拒みませんが、膨大な量であるため、自然消去してしまいます。
ですから、メモリーを圧縮し、整理して記憶に残しやすくする工夫が必要になります。
指導する側から見て気付くことに、この2つの脳の領域ですが、3次元的または3人称
的な問題は思考する領域が役割負担しないと、お手上げ状態になるようです。
平面図形、計算問題までは記憶する領域をフル回転させれば、なんとか対応する。
しかし、展開図と積木、早さと時間と点の移動・面積の関係、月と太陽と地球と公転の関係、
作者と作品背景と作品内の登場人物と生徒自身の関係などは思考する領域が処理しないと
同系統の問題をやるたびに、問題ごとの解法を覚えようとしてしまい、記憶する領域を
占領してしまう。
算数の難解な問題が解けなかったり、過去にあれだけ訓練した項目が全然身についていない
こと、あるいは国語の読解と記述がいつまでたっても苦手なことって、
生徒が勉強を怠けているのでも、練習が足りないのでも、教材が不適格なの
でもない。思考の領域に学習処理をバトンタッチさせてないだけのことが
本当に多いのです。
傾向ですが、授業ををよく聞き、長時間勉強することに不満を言わず、
両親の言いつけをきちんと守る「良い子」ほど、記憶する脳の領域を酷使
しています。
すこし変わり者、悪く言えば偏屈者の方が記憶する脳を旨く使うようです。
私のブログを見にこられる皆さんですから、以上のことなど百も承知でしょう。
イッセイ会では、上記の仕組みに合わせた脳の領域別学習に徹しているのです。
「教えない指導」をモットーにしていますが、「今週はテキストの何ページ
から何ページまでやっておきなさい」という短絡的指導ではないのです。
算数で把握しなければならない単元は80単元ほどありますが、「今週学習する単元は、
4つの重要な糸口があります。先に4つの糸口を案内しておきますの、その糸口を
常に頭に浮かべて、組みたてながら例題理解に挑戦しなさい・・・」となります。
記憶する領域を使用する歴史科目は、「テキストをみて重要だと思うところを
覚えやすいように書き出して暗記しなさい」などという指導はいたしません。
「次の項目でテストに出る語句は、案内した65個の語句です。最初に65個の
語句を10回暗唱してから、テキストを読み、暗唱した語句がでてきたら、その部分
に注目して読みながら語句同士を結びつけてください。結びつけが頭の中で完成したら、
暗記表のいつ、誰が、何を、どうして(どんな)に書き出して暗記しましょう」となります。
暗記することを表にしてプリントで渡すと、語句同士の結びつきがなくなるため、
生徒にとって、脈絡のない不規則に並ぶ数字を暗記するように感じるようです。
テキストから入ると、全てのページ、全ての文書を暗記しようととらえるようです。
いずれも、記憶する領域には効率がよくない。記憶しても長続きしない。
よって、必要な語句を先に与え、それを生徒にテキストで結びつかせ、
パターン表に規則正しく書かせて覚える。これがイッセイ会式暗記法に
なりました。
現在、新6年生26名、新5年生28名を指導していますが、私の目からみて、
新6年生になるころには、生徒だれもが、脳の領域をうまく使いこなすエキスパート
になってくれます。この生徒たちには、学習すべき単元とともに常に糸口を毎週
連絡し、2週間後の項目テストで理解の弱い項目の指摘と思考する指示や方法を
案内してます。
学術指導の諸先輩方や脳科学者の皆様は異論を持たれると思います。
しかし、このやり方で長年指導しているのがイッセイ会なのでご容赦ください。
今日は、少し長い文章でしたね。すみません。
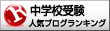
←応援お願いします。
 [0回]
[0回]


