この科目は苦手、この単元は苦手、この項目は苦手。
かならず、どの生徒も苦手意識は持ちますし、存在します。
一旦、苦手意識を持つと克服するのは大変。マインドコントロール
を含め、大好き意識に変えなければ解答力、正解率は上昇しません。
そのような「苦手意識」という解釈ですが、この解釈の発生についても
かなり以前より調査し続け、原因の究明、対処の仕方を用意できました。
問題を解くとき、解けない場合や間違った場合に苦手意識が出来るのか?
それとも、既に問題を解く前から苦手意識を持つのか?
調査の結果から話しますと、苦手意識は先発的要因で定着するという
結論に至りました。
学習ごとで言いますと、それは科目に関係なく、スポーツや習いごと、
趣味や趣向に関することも含め、「最初に体験する」時点では、うまく
出来なくて当然ですから、初めて体験することが、上手に出来なくても
「苦手」などとは感じません。楽しければ、もう1回!とか次は成功
さるぞ!とリトライできます。大人も子供も同じ感情でしょう。
話しはそれますが、お酒が苦手な人がいます。これは苦手意識ではなく、
実際に体が受け付けない正真正銘の「苦手」です。
苦手意識とは、最初に体験する時に、または体験する以前から、
既に否定的な情報を受けて体験してしまった最初の体験に過ぎないのです。
次の問題は難しいぞ~。
この項目は理解しにくいぞ~。
跳び箱の10段以上は怖いぞ~。
逆上がりは簡単にはできないぞ~。
体験する前から、または体験する最中で、このような
情報が先生、保護者、友達から注がれます。
誰々ちゃんも、出来なかったんだって。
あの先生も子供のころは、そこが出来なかったんだって。
こんなことを聞かされた生徒は、「じゃあ私には出来ない
かも知れない」と感じるはず。
初めて体験した項目で不正解だった子どもに、「こんな基本問題も
出来ないの。この項目は文章題が中心で、もっと難しくなるのに」なんて
注意したら、「私は基本問題も解けないから、文章題なんて出来ない」
と苦手意識を持つに決まっています。
否定的で克服困難な事前情報や環境情報を得た場合、学習脳は、
否定的情報=困難=苦手=嫌い・危険というレッテルを貼ります。
こうして出来た苦手意識は、理解して解くという思考回路に入らず、
拒否して受け入れない、防御の機能によって遮断されてしまう。
途中でそれた話し「お酒が苦手」の件ですが、摂取したことで
気分が悪くなったり生命の危険を感じた「実体験から苦手」を学んだ
ため、脳は生命維持の機能を前面に押し出し、拒絶する機能を優先さ
せて、受け入れないようにする。そのとき無意識のうちに、嫌いという
感情をセットにします。また危険や困難なものという信念が出来ます。
苦手、嫌い、危険という意識、感情、信念の防御システムは完璧で、
これにかかるキーワードの情報や体験は、拒否拒絶するのが人間の
脳の役割と思われます。
ですから苦手意識を持つと、危険なお酒を飲まないようにする
という生命維持の機能と全く同じ防御システムが働き、拒絶して
苦手意識の問題を克服できない。ただそれだけのことと実感するに至りました。
怖い体験をした、気分が悪くなった、このような体験をして、危険なことを
実感し、後発的に「苦手」を知り、防御の機能が高まります。
このとき「嫌い」とか「嫌う」、
「困難」、「難しい」などという感情が記憶されます。
ですから、「嫌い」「嫌う」「困難」「難しい」という情報には、そのこと自体を
体験する前から防御のキーワードにかかってしまう。
困難、出来ない、難しいという否定情報により「嫌い」「危険」という
感情が芽生える・・・苦手意識初期の段階
実際に問題を解いて正解できなかった・・・苦手意識が苦手として刷り込まれる段階
ここまで来ると、「嫌い」というレッテルとともに「危険」と感じ、
思考する回路は受け入れを拒否する。
次に全く違う項目の問題でも「苦手」と意識しただけで、拒絶までスムーズに
脳内で拒絶反応が起きる。
この繰り返しで算数という科目全体が苦手、嫌い、拒絶への進む。
楽しい、やりがい、達成感、できる、このような体験は「好き」「好む」「やれば
できる」「自分は出来るので楽しい」という感情が記憶されます。
ですから「好き」「好む」「できる」「楽しい」は吸収し、思考する回路に到達
できる。ですから違う項目の問題も積極的に解いてみようとする。
ここの延長で算数全体が好きで得意な科目に定着していく。
思考する回路の中では「好き」「楽しい」という環境情報をキーワードに
知りたい欲求
分かり合いたい欲求
が優先して、知識と好きという信念、解きぬく信念が生まれます。
思考する回路に入る前に関所があり、「「難しい」、「困難」
という環境情報をキーワードに
生きたいという欲求の安全防御の機能
が優先して、知識を思考回路に届かないようにし、
排除、拒絶という体勢が生まれ「嫌い」という感情が生まれ、
「嫌う」ものは「危険」とすりかわり、嫌うもの全てを
受け入れない連鎖が起きる。
結果を叱らないという信念のうえに指導していますが、
叱ると「嫌い」「難しい」「危険」「困難」と同じような否定的情報を
注いでしまいます。単に出来なかっただけなのに、興味さえ持てば出来る
段階なのに、否定情報と共に「苦手意識」を持たせてしまう。
やがて「苦手意識」は「苦手」と判断され、生きていくうえで危険物と
みなし脳が受け入れを拒絶する。
もっと究極なことを話しましょう。
いつも成績やテスト結果を叱るお母さん。生徒にとって、お子さんに
とって「いつも成績のことで怒るお母さん自体が苦手」と感じると
どうなるか?
そうです。お母さんの言うこと、話すこと自体を「危険」と感じ、拒絶する。
急に、プチきれしたり、反抗したり、聞いているのかどうかわからない態度を
とるようなお子さんになっていませんか?
話しをもとに戻しましょう。
いかに「苦手意識」というレッテルを貼らせないようにするか。
「嫌い」「困難」「難解」という環境情報を与えないようにするか。
これを実行するのと、しないのとでは学習修練度は格段の違いがでます。
前者は停滞しながら、少しづつのレベルアップ。
後者は、ホップステップジャンプの短期大躍進。
イッセイ会のマルテク情報会員になりますと、以上のような情報と共に
さらに細かい日常の対処の仕方などが入手できます。
近日、新規入会を募集しますので、ご期待ください。
ランキングの応援もお願いします。
↓
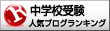
 [2回]
[2回]
PR


