自宅学習で中学受験をサポートしているイッセイ会ですので、
理にかなった学習と効率の良い学習を追及しております。
今回は、後者の効率の良い学習について少しお話しします。
大手広域塾では、宿題を含め大量の設問をこなしているようですが、
それはそれですばらしいこと、生徒さんのがんばりも賞賛いたします。
習うより慣れろ、という言葉があるように、数をこなすことは、
決して無駄ではありません。ひたすら練習、反復することが力になることは
当然であります。
イッセイ会でも練習する設問数は少なくありません。
ただし、「この問題は同じ単元内の類する他の問題へカギとなる重要な問題」
という意味を込めてマークを付けています。
また前回間違えた問題にもマークを付けさせています。
どうしても時間がない場合、もう一度ふりかえりをする場合などに、
必ずやるべき問題としてマーク付け問題を推奨しています。
話しを主題に戻しますが、「守備範囲」という概念を受験勉強に取り入れた
のは、こんな光景からでした。
日頃、電車を使うことが多いわたくしですが、ラッシュ後の電車内は、座席は
一通り埋まっていて、立っていられる方が座っている方より少し少ない状況に
なります。こんな電車内の状況で、後から乗り込んできた方や同じ車内の違う
場所から移動してきた方が、まるで次に席を立つ方を知っているが如く、席を
立つ方と入れ替わりに着席されます。
別に、わたくしが席を取れなかった悔しさを書こうとしているのでありません。
なんで、後からきた方が席を取れるのか。その疑問を解くため、毎回観察して
いました。その結果、後からきて席をとれる人は、他の立っている人との間隔が
ほどよく多めに取られていてところに立つ。すなわち自分の守備範囲を他の人より
少し多くとっているのです。
それでいて、立ち位置のバランスにも長けていることがわかりました。
要は、守備範囲を極端に広げず(人より多めにとり)、効率のよい位置に立つ。
10年前まで、わたくしも可能な限り問題数をこなす指導をしてきましたが、
守備範囲を広げる意味合いを、効率のよい守備範囲という見方に置き換えて
指導するに至りました。指導する問題数は決して少なくありませんが、意味ある
問題や重要な問題、カギになる問題の配慮が加わっています。
また、自信をもって「この問題が解けるなら、次の問題は練習しなくてもよい」
という決断がつけられます。
このようなことをすすめられるのも、実は前者の理にかなった学習が
根底にあるから。
理解する部分と暗記する部分の区分けは、理にかなう学習の根本ですので、
次の機会にでも書きたいと思います。
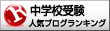
←応援おねがいします。
 [0回]
[0回]
PR


