日頃、算数の効果的学習指導に注力している私ですが、何よりも
大切な学問は国語読解力だと思います。
読解、記述、心情描写。この力に長けていなければ、算数の文章題
も理科実験内容描写も解読できません。
私ごとで恐縮ですが、私は小学6年の春まで、国語力に自信がなく、
テストでは常に良い点が取れていませんでした。
当時、教えないことで有名な塾に通っていましたが、国語力に乏しい私を
見かねた講師陣が、与えくれたたった1つの問題が、私の国語力の突破口
(自信)に結びついたことをお話しいたします。
当時出された問題は、童謡で有名な三木露風の「赤とんぼ」という詩。
夕焼け小焼けの赤とんぼ・・です。
この詩の全節が書かれたプリントを渡され、「この詩の中で印象に残った
言葉を題材に、この詩の解釈を自分なりに表現しなさい」という問題です。
注釈として、姐や(ねえや)は奉公で下働きをしている、よそから来た娘さん。
作者は5歳の時に両親が離婚し、母とは離れ祖父に引きとられ、祖父の家に
奉公に来ていた姐やに育てられていた。とありました。
当時小6の私は、精一杯の解釈を行い解答しましたが、その内容が斬新で
あったため、講師陣は関係者を通して「我が生徒の寄稿」という形で学術
発表してくださいました。その結果、多方面から評をいただき、自信と共に
国語力の大切さを感じたのでありました。
参考に、当時の解答を記します(原文ではありません、少々大人の言い方
に直しています)。
この詩で印象に残るのは、「小焼け」という言葉です。
結論から言うと、普段使わない「小焼け」という言葉は、作者が大人になって
気がついた「初恋心」だと思います。
詩の解釈ですが、4節目の竿に止まっている赤トンボと広がる夕焼け
を見て、幼き頃の同じ情景をはたと、思い出したところから始まります。
それが1節目の夕焼け小焼けに掛かります。
幼き頃に見た夕焼けに舞う赤とんぼは、負われて見たとありますので、幼き作者は
5、6歳でしょう。おんぶしてくれていたのは、姐や(ねえや)です。
姉ではなく姐やなので、年季奉公で身を寄せて下働きをしている、よそから
来た娘さん。
年季明けに15歳で嫁に出されるくらいなので、姐やの実家は貧しい家庭なの
がしのばれます。子守りをしてくれた姐やは当時10歳前後でしょうか。
一見、幼き頃を回想する詩に感じますが、大きな心のうねりを感じます。
それは、2節目にある「桑の実」を摘む場面。
子どもの頃の回想に桑の実を登場させた意味は、桑の実の味です。
食べたことがありますが「甘くてほろ苦い」。
そして2節目の締め言葉が「まぼろし」。
甘くてほろ苦い桑の実、そしてまぼろしとは、初恋だと思います。
おそらく当時の作者は、そのもやもやした気持ちが何なのかわからなかった。
それを表すのが小籠。籠はゆりかごを連想させる母の象徴。
作者三木露風は、5歳の時に両親が離婚し、父方の祖父に育てられて
います。その祖父の家に奉公にきていた姐やに離れ離れになった母への想いを
重ねていると勘違いしていた。
姐やが嫁いだ後、いつしか便りが来なくなったことまで覚えているということは、
姐やに対する特別な想いがあったのでしょう。またこの便りの意味には、
本当の母からの便りも来なくなったことが重ねられている気がします。
更に嫁いだのは姐やだけでなく離婚した母が再婚してしまったことも表現したかっ
たのかも知れません。
姐やへの想いが、大人になって夕焼けの中、赤とんぼが竿に止まる情景を見て
幼き頃の初恋心だったんだと気がついた。
4節目で、竿に止まっていたのは赤とんぼですが、実は止まっていたのは、
大人になるまで心の中にしまいこんでいた当時では気づかなかった初恋心。
その作者の初恋心は、時間を超越した壮大な茜色の夕焼けに照らされた
空とは比べ物にならない小っぽけな「小焼け」だと思います。
このときの答案をひねり出した経験を申しますと、自分の中に何人もの
自分が現れ、お互いに解釈を論じ合ったり、意見を交換しああったりしたこと。
ただ一人の私が感じたのではなく、描写や解読には、自分の中に何人もの
意見交換できる自分を置き、やりとりしながら考えていく楽しさが必要です。
応援お願いいたします。
↓
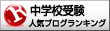
 [0回]
[0回]
PR


