自宅学習の生徒さんだけでなく、通塾生のマルテク会員の
みなさんからも、よく質問されることについて、お話しよう
と思います。
よく受ける質問とは、「算数は沢山の単元があるのですが、
どこが重要で必要なのでしょうか」または「どの単元から
学習すればよいのでしょうか」です。
この質問の根底には、必要ない単元は省略させたいという
願望もあるようです。
残念ながら、どの単元も省略させたり、手をつけないで済ます
ことはできません。しかし効率よく効果的に学習することは
できます。
自宅学習の生徒さんは、基本にしている参考書の目次の
順番で一通り学習していることでしょう。通塾生なら、
塾の教科書の目次順で学習しているはずです。
履修のための学習は目次順で手をつけるしかありません。
参考書にしろ、塾の教科書にしろ「その順番」が後の
単元に上手にかかるように表現されているからです。
問題は、振りかえりの段階です。ここで、手を加えるのと
再度、最初からテキストの順番で行うのとでは大きな差が
生じるのです。
振りかえりの場面で重要なのは算数の系統に合わせた
単元を同時に進行させること。
算数の系統というと、計算、一行題、応用問題という
分け方ではありません。当会独自の系統分けですが、
出題する側の立場で考えた算数の区分けです。
その区分け的系統とは、
周期数論
比較数論
早さ数論
幾何
計算力
の5系統です。
周期数論とは、
順列、数列、規則性、組み合わせ、場合の数に始まり、
過不足算、暦算。
比較数論とは、
比例、連比、代入算、消去残、濃度、商い、和差、植木、
仕事、平均、つるかめ算。
早さ数論とは
通過、旅人、流水、進行グラフ、点の移動
幾何とは
平面図形の面積、角度、辺の長さ求解、立体の表面積、
体積、底面積の算出。
計算力とは、
四則計算、分数の計算、単位の読み替え(haや縮尺)、
特殊な分数の計算。
1回目の振りかえりでは、上記の5系統を同時に振りかえり
させます。少なくとも5系統のうち同時に3系統をずらしな
がら毎日すこしづつ基礎問題中心に3問程度。
2回目の振りかえりでは、基礎1問に中程度2問。
3回目の振りかえりでは、中程度1問に高度2問。
4回目の振りかえりでは、高度1問に2つの系統
にかかる部分を2問学習します。
5回目は2つにかかる系統ばかり3問。
幾何と比較数論がかかる「面積比、底辺比、相似比」。
幾何と周期数論がかかる「積み木算」「マッチ棒順列」。
幾何と速さ数論がかかる「時計算」「水槽に錘」。
比較数論と早さ数論がかかる「はやさつるかめ」。
周期数論と早さ数論がかかる「ダイヤグラフ」。
超難問とは、2つ系統がかかる分野ですので、3回目の
振りかえりまでに区分けごとの学習をマスターした
ほうが、思考しやすいのです。
また区分けして振りかえりをすることで、不得意な分野
自体とそれに関わる2系統がらみの分野もチェックする
ことができます。
そんなに振りかる時間があるかという質問も受けますし、
実際に心配も生じます。しかし、算数はやらなければ克服
できません。
5系統各3問で1日15問を10日間。1日3系統で
1日9問なら15日間。
全単元を半月で復習できる量です。
間違い解き直しを含めて1日最大でも1時間半が目安です。
現在、新6年生は、この3月に算数の全単元をひと通り
履修完了するころだと思います。学校別過去問に本格的とりかかる
8月までの5ヶ月間に最低5回の振りかえりを1セットやりたい。
できれば、2セットやるべきです。
2セット目の振りかえりは「基礎部分は飛ばせるくらい」になれれば
よし。ここまで振りかえりをすると、どこが不得意か必ず判明します。
この不得意分野を8月から行う過去問と合わせて学習すれば、
鬼に金棒になるのです。
応援お願いいたします。
↓
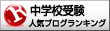
 [0回]
[0回]


